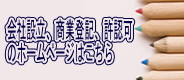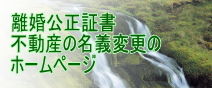遺言書について - 港区芝浦(田町駅)の遺言、相続登記、債務整理、離婚、成年後見
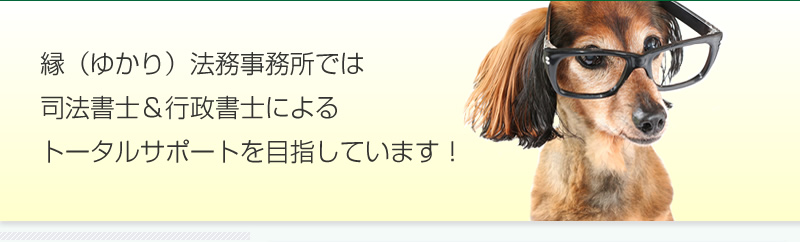
遺言書とは
遺言書を作成する理由/遺言者の資格/遺言がない場合/
遺言書でなにができるのか/財産とは/遺言書Q&A
(1) 遺言書を作成する理由
自分の遺産に関しての家族による「争い」の防止。そして何より「自分の思い」を伝えるものとして最適なものだからです。
(2) 遺言者の資格
15歳以上の者。成年被後見人の場合は医師2人以上の立会い(証明)が必要です。
(3) 遺言がない場合
▲このページの上へ(4) 遺言書で何ができるのでしょう
- 相続分の指定・第三者への指定の委託
相続分の指定とは、「全体の5分の1を相続させる」等の持分を決める方法。
第三者への委託とは、自分の信頼している人に相続分を決めてもらう方法。 - 遺産分割方法の指定・第三者への指定の委託
遺産分割方法の指定とは、遺産(土地等)を具体的に誰に相続させるのかを指定する方法。第三者に委託することもできます。
- 遺産分割することを5年以内の期間で禁止
- 遺言執行者の指定・第三者への指定の委託
遺言執行者とは、遺言に基づいて遺産の処理を行う者。
相続人の代理人。 第三者に遺言執行者を決めてもらうこともできます。 - 後見人・後見監督人の指定
未成年者に対して最後に親権をもつ者(管理権を有していること)は、遺言にて未成年後見人を指定することができます。
- 遺留分減殺方法の指定
遺贈に遺留分減殺請求をした場合、通常全ての遺贈の価格から持分割合に応じて減殺するが、遺言によって特定の遺贈から減殺するように指定することができます。
- 相続人相互の担保責任の指定
相続人は、遺産のみならず負債も相続するため担保責任も相続します。
その担保責任の割合に関して指定することができます。
- 遺贈(包括遺贈、特定遺贈)
- 包括遺贈
遺産の全部又は一部を一定の割合(例 持分5分の1)で相続させる方法。相続人と同一の権利、義務がある。
- 特定遺贈
特定の具体的な財産(例 甲の土地)を相続させる方法。
- 包括遺贈
- 財産の処分・寄附行為
寄附行為とは、遺産の全部又は一部を財団法人等に寄附する方法。
- 認知
認知とは、婚姻関係にない父が子(非嫡出子)を自分の子と認める行為。
- 相続人の廃除・廃除の取消し
相続人の廃除とは、遺留分のある推定相続人(兄弟姉妹は除く)に対して、(1)遺言者に対する虐待、重大な侮辱又は(2)その他の著しい非行が行われた場合に家庭裁判所に請求して相続人から外す行為。
*例
・情婦のもとに走り、父の病が重いとの通知があっても戻らず見舞状すら よこさないのは侮辱にあたる。
・遺言者に対する言動(虐待・侮辱)が一時の激情にかられたもので、将来反復の可能性がない場合は非行とはいえない。 - 祖先の祭祀主催者の指定など
- 遺骨を海に散骨してほしい
- 葬儀は密葬にしてほしい
- あの人に連絡してほしい 等
▲このページの上へ
(5) 財産とはどういうものでしょう
- 土地、建物
- 現金、預金
- 有価証券(株券、債券、手形、小切手、商品券等)
- 権利(借地権、借家権、会員権、営業権、著作権、特許権、電話加入権等)
- 受取人が遺言者の生命保険
- 物品(自動車、宝石、貴金属、骨董品等)
- 負債(借金、ローン、クレジット等) 等
▲このページの上へ
(6) 遺言書Q&A
| 遺言できる人はだれ? |
- 満15歳に達した者は、遺言をすることができる(民法961)とされています。
- 2人以上が同一の証書で遺言をすることはできません。
- 成年被後見人である場合、遺言の制限がございます。
- 認知症等(意思能力がない)の場合は基本的に遺言はできません。
(医師の診断等で意思能力に問題ないことの証明がされれば可能です)
| 遺言の種類はどういうがあるの? |
普通方式と特別方式がございます。特別方式は、遺言者の死亡が危急に迫っている場合や、一般社会と隔絶した場所にあたる場所にあるため普通方式によることができないときに、特に要件を緩和して認められる方式です。一般的に「遺言」として言われているものは、普通方式になります。
| 複数の遺言がある場合どうなるの? |
![]()
作成時期の異なる複数の遺言がある場合、お互いに内容が抵触する部分については、
最後のものが有効な遺言となります。
| 検認とはなんですか? |
公正証書遺言以外の遺言については、家庭裁判所にて検認の手続きが必要となります。これは封のしてある遺言を裁判所で開封することによりそれ以降の変造を防止する効果があります。登記に使用する場合は検認がないと申請できません。
| 誤って開封してしまったらどうしたらいいの? |
開封後であっても検認はできますので、すぐに検認してもらいましょう。 検認は遺言の有効、無効を判断するものではないため、「検認が無いため遺言書が無効」となる訳ではありません。しかし開封後に何か手を加えたのでは、と疑いをかけられる恐れもあるので未開封で検認することが望ましいです。
| 証人となれる人はどんな人なの? |
証人とは、未成年者、成年被後見人、遺言者の親族(4親等内)、推定相続人や受遺者(配偶者、直系血族を含む)、公証人の関係者(書記等)はなることができません。 証人がいない場合は当事務所で証人を用意しますのでご安心ください。
| 遺言執行者とはどういう人なの? |
遺言書に書かれている内容を実現するために、遺言を執行する権利を持つ人のこと です。そして遺言執行者のみが、認知及び推定相続人の廃除又は廃除の取り消しの手続きができます。ゆえに上記の事項を遺言書に記載される場合は遺言書で指名しておくほうが望ましいかもしれません。指名されていなくても、後から裁判所に選任してもらうこともできます。遺言執行者は、未成年者および破産者を除いて、誰でもなることができます。 遺言執行者を選任しておくと相続自体がスムーズに進むこともあります。ご気軽にお問い合わせください。
| 遺言書の方式のうちどれが一番よいのですか? |
やはり公正証書遺言が一番安心でしょう。検認の必要もなく、内容も無効となる危険が少ないためです。
| 一度作成した遺言書を変更することはできますか? |
もちろん変更することができます。しかし公正証書遺言の場合は再度費用がかかります。