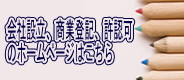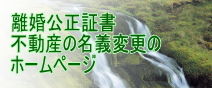用語説明について - 公正証書遺言、相続登記の縁法務事務所
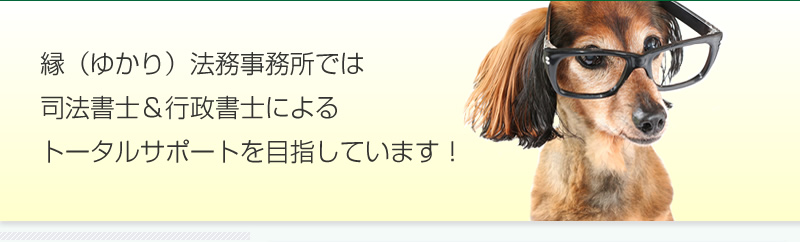
用語説明
- 民法に決められた相続分のこと。
- 法定相続
- 被相続人によって残された金銭に見積もれる全てのもの。負債も含む。
- 相続財産
- 亡くなった人。
- 被相続人
- 現時点において相続が発生した場合に相続人となるべき人。
- 推定相続人
- 推定相続人が被相続人死亡以前に既に死亡していたなどの場合に、
代わって推定相続人の子が相続人になること。
- 代襲相続
- 法定相続とは異なった相続分にすることを相続人の協議によって
すること。
- 遺産分割協議
- 相続財産を遺言書のとおりに分配することを行う人。遺言書で指名することもできるし、相続開始後に家庭裁判所に選任を申立てることもできる。
- 遺言執行者
- 法定相続人(うち兄弟姉妹は除く)が相続財産の受け取ることができる最低限の割合。
遺留分を侵害している場合には、不足分を請求できる
(遺留分減殺請求)。
- 遺留分
- 遺言書によって相続人以外の者へ特定の物や相続分を与えること。
(相続人である場合も遺贈すると文言があれば遺贈になります)
- 遺贈
- 家庭裁判所での手続き。相続人に対し、遺言の存在とその内容を知らせると同時に、検認の日現在における遺言書の内容を明確にし、遺言書の偽造・変造を防止するための手続き。
遺言書の有効・無効を判断する手続きではありません。
- 検認
- 相続財産のすべてを相続しますということ。負債も相続するため負債が多い場合は相続人の財産から支払う必要があります。
特に手続きの必要はありません。
- 単純承認
- 相続財産がプラスの場合は受取るがマイナスになった場合は相続人の財産から支払う必要をなくす手続き。
負債がどのぐらいあるのかわからない又は負債のほうが多くなるかもしれないというときに利用します。
- 限定承認
- 家庭裁判所に相続を放棄することを届け出ること。初めから相続人ではなくなります。
- 相続放棄
- 被相続人から生活資金の援助や結婚に際する持参金、事業を始める資金提供など、特別の財産的利益を受けている場合。
相続人のなかに特別受益を受けた人がいる場合には、特別受益を相続財産とみなし、加算して分配する。
- 特別受益
- 被相続人の財産の維持や増加に貢献した相続人は、法定相続分以外に貢献分の財産の受け取りを主張できること。
相続開始時の財産から寄与分を控除した残額を相続財産とみなす。
- 寄与分
- 婚姻関係にある男女間に懐胎・出生した子のこと。
- 嫡出子
- 虐待、侮辱やひどい非行があった場合、その法定相続人から相続権を剥奪すること。
- 相続人の廃除
- 被相続人・相続人を殺そうとしたり、強迫して遺言させたり、遺言書を偽造・隠匿したりなどした場合、その法定相続人は相続人たる資格を
失うこと。
- 相続欠格
- 戸籍の表示、氏名、住所、住所を定めた年月日が記載され、本籍地の
市区町村で管理しています。
戸籍の附票には、住所の変遷が記載されているため、住所を証する書面や住所の変更を証する書面として使用されます。
- 戸籍の附票
- 成年後見人などがきちんと後見業務を行っているか、本人の保護に支障がないか、監督する人のこと。法定後見では、必ずしも監督人が選任されるわけではありませんが、任意後見では監督人が必ず選任されます。
- 成年後見監督人
- 生活や療養看護に全般的な身上を監督し保護すること。
- 身上監護
- 行為の結果を弁識することができる精神能力。
意思能力のない者の行為は無効。
- 意思能力
- 自らの行為により法律行為の効果を確定的に自己に帰属させる能力。
成年被後見人等は行為能力が制限されるため取消すことができる。
- 行為能力
- 親権者。
親権者がいないとき、または親権者が管理権を有しないときは後見人。
- 法定代理人
- 利益相反行為等で家庭裁判所が選任しある特定の行為について
代理する人。
- 特別代理人
- 後見人と被後見人との間で後見人が被後見人の代理でした行為が後見人の利益になるような場合。
- 利益相反行為
- 任意後見において後見開始までの生活状況や身上の様子を定期的に
確認する契約。
- 見守り契約
- 脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力なとの障害がおこり、
普通の社会生活がおくれなくなった状態のこと。
- 認知症
- 財産の管理や処分を他人に委託し、委託された人は、その財産から生じる利益を決められた人(受益者)に分配します。財産を持っている人が判断能力が衰えた時に、その人自身を受益者とする信託、障害者の子供のための活用などが考えられます。
- 信託
- 一定の期間内であれば消費者が事業者との間で申込み、または締結した契約を、一方的に撤回・解除できるというもの。撤回・解除は必ず書面で行わなければならない。
- クーリングオフ
▲このページの上へ